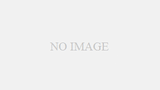我が家は長男次男、共に自閉症です。
昨日は次男は保育園で夏祭りがあったのですが、「甚平を着ること」と「みんなで踊ること」がどおおおおおおおしてもイヤで、楽しくなくて、頑なに拒否。いくつつかのやり取りの後、今回は欠席しようとなりました。集団特有の「みんなで楽しむ」を同じように楽しめない経験は今までも幾つかありました。理由やその感覚的なところははわからないし、自分に置き換えたらどういう種類のものかなーなんて考えるんだけど、とにかく次男にとっては、どうしてもイヤな類のものなんだろうなと思います。
なんで参加できない?みんなもやってるよ?という声かけは意味をなさず、やはりそこに大きな苦しさを抱えている子へ。今回は
《みんなで一緒に》ってなんだろう?
自立支援員(&不登校支援員)の立場から、《一緒》って色々あるよね、というところ。
3つの《一緒に》を考えながら、支援の方向を探っていきたいと思います。
柔軟な《一緒に》を考えていけたらいいなと思います。
1「同じ」
「あなたの持ってるものと私の持ってるもの「同じ」=《一緒》だね」というような一緒。
「みんなと同じ体操をやりましょう」というときは、みんなと同じ体操の動作をやってくださいということになる。「みんなで挨拶しましょう」は、声を揃えてみんなでおはようございますと言う、「みんなで食べようね」は、みんなで集まって決まった時間に決まった場所で一緒に食べることをする、など。集団活動において、特に学校生活ではそういう一緒は多いかもしれません。
2 「ある目的」に向かって共同で何かをすること
「その場に一緒にいながら、ある目的に向かって共同で何かをする」これも《一緒に》ですね。
「一緒に掃除しよう!」とか。
みんながホウキばかりしてても進まない。ホウキをしてる人もいれば、ちりとりをする人もいる。誰かが雑巾がけをして、机を移動する人がいて、、、という役割分担がある。みんなが同じことをやるのではなく、同じ目的を持った活動を、役割を持ってやること。これも「一緒」です。野球やサッカー、チームスポーツもこれに当たります。
空気を読むことが苦手な子、情報が多くなると処理が苦しい子には、支援や工夫が必要になるかと思います。また、役割のある活動において、得意な役割の時はいいけれど、やりたくない仕事の時に、気持ちの折り合いのつけ方をどう持っていくか、工夫が必要かなと思います。(そこは大人だってそうですよね…)
★この2つにどうしても馴染めない子がいる
集団生活においては、どうもこの2つの《一緒に》にどうしても馴染めない子どもがいます。みんなが楽しくやってる活動なんだけど、どうしても1人だけ楽しめない。みんなはよく分かってるんだけど、1人だけよく分かってない。ということ。
1人だけやらない、一緒にやりたがらない。そういったとき、大人たちは、なるべくみんなと過ごさせたいなって思うかもしれない。私たちは「みんなでやったこと・やることに」を大きな価値を生みがちなので。
ただ、子どもからすると、みんなは楽しく過ごしているのに自分だけがそうじゃないということがあると、疎外感を味わったり、自信を失ったりすることが往々にあります。
もしかすると、感覚過敏の可能性もあるので、そんなところも注意してみてくださいね。
それはさておき
さて、どうしたらいいか。
一つは「別の場所で別のことをやる」という考え方もありますね。特別支援教室とか通級指導教室とかでやられていることはそういうこと。
もう一つは
3 みんなと同じ空間にいながら、別の活動をする
不登校支援の現場では、当たり前にある風景。苦しさを受け入れ、みんなをひとくくりにしない、同じ活動を求めない。
みんなが鬼ごっこをしているとき、ジャングルジムで遊んでる。みんながカッターナイフを使って作業しているとき、自分はハサミを使って作業する。みんながこの問題集をやっている間、自分は別の問題集をやる。(合理的配慮とも言われますが)同じ空間にいながら、別のことする。そういう存在の仕方も《一緒に》と言えます。
結婚生活の長い夫婦が同じ家で、それぞれに別のことをしているなんてよくありますよね。けど《一緒に》住んでいるわけです。
遊びの中だと、平行遊びなんて言い方もしますが、平行遊びの中で、同じことをする子がたまたまいて、そのうち自然に《一緒に》が始まる。幼少期においては、よくある自然な他人との関わりの姿ですし、そこで、人との距離感を学んだり、コミュニケーションを学んだり、《一緒に》を楽しむプロセスになってくる。そんな経験をたくさんしてほしい。これは学童期においても大事なことだったりします。
同じ空間にいながら、自分を尊重してもらえること、分かってくれる、自分の存りかたを保障してくれる集団で育った子は、自分を大事に感じます。
「学校に馴染めない」という不登校の子に、周りと同じ空間にいながら、自分の過ごしたいように過ごす時間や空間を十分に保障してあげた結果、2の《一緒に》に少しずつ抵抗がなくなってきた子がいます。(これはよくあるパターンです)
《一緒》というのは、全く同じことを同じようにする」から「同じ空間にいながら、別のことをする」まで幅広いこと。
どこまで求めて、どこまで一緒にを広く捉えるか、そこを見つけていくと、その子の今の姿がより鮮明に見えてくるかもしれません。